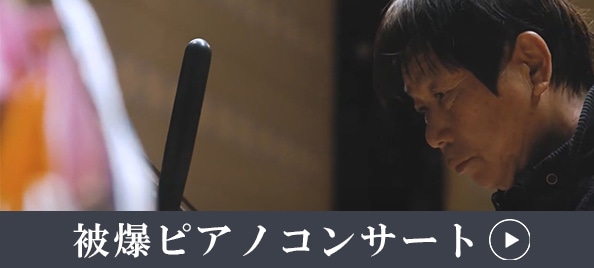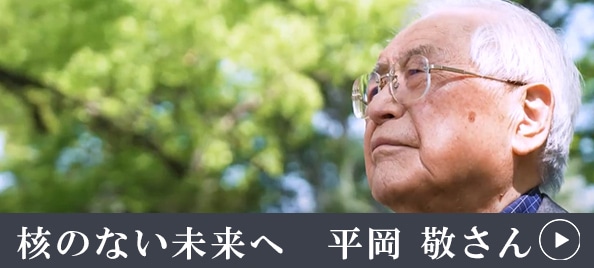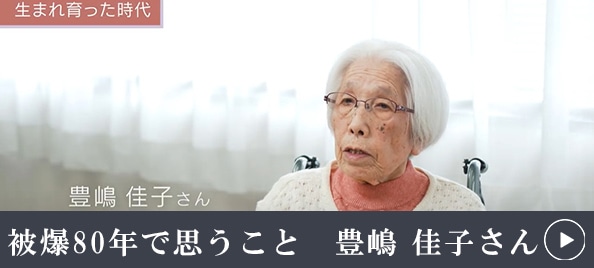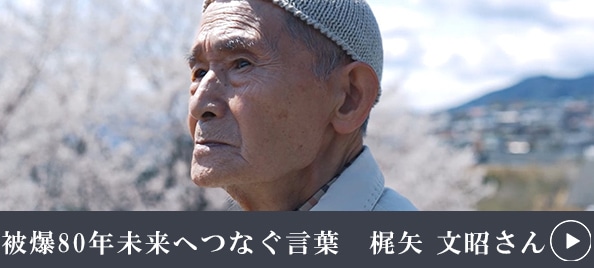碑めぐりガイド
「ヒロシマ」をご案内します。
市内各所に点在する、被爆の実相を伝える「碑」をめぐり、そのいわれと「碑」に込められた「思い」をご案内いたします。訪れた方と一緒に、「平和の尊さ」と「ヒロシマ」を実感、そして後世の人たちに「ヒロシマを語り継ぎたい、そんな思いで活動をしています。

イラスト上の地点をクリックすると説明文や動画をご覧いただけます
イラスト上の地点をタップすると説明文や動画をご覧いただけます
- 爆心地・島病院
-
爆心地・島病院

建立年月日 1933(昭和8)年8月31日(開院) 形状(当時の島病院) 近代的なレンガ造2階建てで、玄関の両サイドの丸柱と円形窓が印象的な建物 説明板 「テニアン島から飛来した米軍機 B-29「エノラ・ゲイ号」によって人類史上最初に投下された原子爆弾は、この上空約600メートルでさく裂しました。爆心直下となったこの一帯は約3,000度~4,000度の熱戦と爆風や放射線を受け、ほとんどの人びとが瞬時にその生命を奪われました。時に1945(昭和20)年8月6日午前8時15分のことでした。」 爆心地
当時:広島市細工町(さいくまち)29-2 島病院
現在:中区大手町1丁目5-24 島内科医院南側大手町第3駐車場原爆さく裂の瞬間
T字型の相生橋を投下目標にしたとされる原爆は、島病院の上空約600mでさく裂しました。さく裂後、中心温度が摂氏数百万度の小型の太陽ともいえる火球が発生しました。1秒後には半径200mを超える大きさとなり、爆心地周辺の地表面の温度は3,000度~4,000度にも達しました。爆心地から100m地点での爆風は秒速約280mでした。(鉄の溶ける温度は約1,500度、太陽の表面温度は約6,000度)島病院の被災状況
被爆当日、島病院の院長(島薫氏)は出張診療で不在だったため難を逃れました。建物は瞬時に壊滅し、約80人と推定される患者・看護婦などの病院内にいた人は全員が亡くなり、姿は跡形もなかったといます。 - 原爆ドーム
-
原爆ドーム
竣工年月日 1915(大正4)年4月5日(開院) 建立者 広島県 (1953(昭和28)年広島市へ譲渡) 設計者 ヤン・レツル(現在のチェコ出身の建築家) 形状 「レンガ(一部鉄筋コンクリート)モルタル仕上げ、玄関部分は石造りで地上3階一部5階建て地下1階。セセッション様式と呼ばれる建築物で曲面を多用しているのが特徴。 原爆ドームは、広島県物産品の販売促進を図る目的で、 広島県物産陳列館として建てられました。県下の物産品の展示・販売のほか、 博物館・美術館としての役割も担っていました。1933(昭和8)年には、広島県産業奨励館と名前を変え、1943(昭和18)年12月の聖戦美術傑作展を最後に業務は廃止され、内務省中国四国土木出張所や広島県地方木材・日本木材広島支社などの統制会社の事務所として使用されていました。
1945(昭和20)年8月6日午前8時15分原爆の投下により、建物は一瞬にして大破して天井から火を吹いて全焼し、約30人余りの人々は全員死亡したと伝えられています。
爆心地に近く爆風がほとんど真上から突き抜けたため、壁の一部は倒壊を免れ、鉄枠の残骸が残りました。 その形から「原爆ドーム」と呼ばれるようになりました。ドームの保存については、意見が対立しましたが、1966(昭和41)年に広島市議会で永久保存を決定、広く募金を呼びかけて、これまでに5度の保存工事が行われました。(2023年(令和5)現在)1996(平成8)年には、世界遺産に登録されました。 登録名称は「広島平和記念碑(原爆ドーム)」 です。
- 原爆犠牲ヒロシマの碑
-
原爆犠牲ヒロシマの碑

建立年月日 1982(昭和57)年8月5日 建立者 原爆犠牲ヒロシマの碑建設委員会 制作者 芥川永(あくたがわひさし)(当時・比治山女子短期大教授) 建立の目的 原爆により犠牲となった人々の叫びを永遠に記し、ヒロシマの心をあらわすとともに、 戦争の悲惨さと核兵器廃絶の課題を学び、平和への決意を固めるため。 碑文
「天がまっかに 燃えたとき わたしの からだは とかされた
ヒロシマの 叫びを ともに 世界の人よ」
(当時・安田女子高校生蔵田順子さん原案)爆心地に近い原爆ドームそばの元安川河床には、原爆の熱線で表面が溶けた瓦がたくさん埋まっていました。1977(昭和52)年以降、 平和記念公園一帯で平和学習を続けていた広島県高校生平和ゼミナールの生徒たちは、数千点に及ぶこれらの瓦を掘り出しました。
1981(昭和56)年、広島市が元安川の美化工事にのり出した時、彼らは原爆瓦の保存を訴え、「原爆瓦で平和記念碑を作ろう」と全国へ呼びかけ、作られたものです。
戦争も原爆も知らない世代が中心となって作りあげた碑です。 - 原爆供養塔
-
原爆供養塔
建立年月日 1955(昭和30)年8月5日 建立者 広島戦災供養会(広島市) 制作者 石本喜久治(いしもときくじ) 建立の目的 氏名不詳や一家全滅などで引き取りてのない遺骨を供養するため。 このあたりは中島本町という繁華街で、慈仙寺というお寺があった場所です。
原爆投下後、 慈仙寺も焼けてしまいましたが、爆心地に近いこの付近には遺体が散乱し、また川から引き上げられた無数の遺体が運ばれて荼毘にふされました。1946(昭和21)年市民からの寄付により、仮供養塔、仮納骨堂・礼拝堂が建立され、引取り手のない遺骨が安置されました。その後10年経った1955(昭和30)年広島市が中心となって、老朽化した施設を改築し、各所に散在していた引取り手のない遺骨もここに集め納められました。その数は約7万柱といわれています。
その中には、氏名が判明しながら引取り手がない骨が813人(2024年現在)あり、広島市はこの名簿を毎年全国の自治体や被爆者団体に発送して、公開し遺族を探しています。
1946(昭和21) 年以後、毎年8月6日の早朝からこの場所では、さまざまな宗教・宗派の供養慰霊祭が営まれています。また、毎月6日には、関係者により例祭がとり行われています。
- 原爆の子の像
-
原爆の子の像
建立年月日 1958(昭和33)年5月5日 建立者 広島平和をきずく児童・生徒の会 制作者 菊池一雄(当時、東京芸大教授)
台座:池辺陽(いけべきよし)建立の目的 佐々木禎子さんをはじめ原爆で亡くなった多くの子どもたちの霊を慰め、世界に平和を呼びかける。 これは ぼくらの 叫びです これは 私たちの 祈りです
世界に平和を きずくための折り鶴の像ともいう。佐々木禎子(ささきさだこ)さん(当時2歳)は爆心地から約1.6キロメートルの楠木町(くすのきちょう)の自宅で被爆して10年後、幟町小学校6年生の時、白血病と診断され日赤病院に入院しました。鶴を1,000羽折ったら願いがかなうことを知り、薬の包み紙や包装紙を使って回復を祈りながら折り続けました。1,000羽近以上の鶴を折ったといわれています。8ヶ月の闘病生活ののち1955(昭和30)年12歳で短い生涯を終えました。折り鶴は死後友人たちに形見として分けられ、その数羽が資料館に展示されています。級友たちは毎月命日の25日に集まることを約束し、「こけしの会」を作りました。会の呼びかけで広島市内の小、中、高の児童会、生徒会が立ち上がり、「広島平和をきずく児童・生徒の会」を結成、被爆者に白血病が多発する中、子どもたちの手で「原爆の子の像」を作ろうと運動を起こしました。広く国内外へも呼び掛け1958(昭和33)年5月5日の子どもの日に除幕しました。
折り鶴は「再び被爆者を作らない」決意の証しとして日本及び外国でも反核のシンボルとして使われています。
- 韓国人原爆犠牲者慰霊碑
-
韓国人原爆犠牲者慰霊碑
建立年月日 1970(昭和45)年4月10日 建立者 広島韓国人原爆犠牲者慰霊碑建立委員会 建立の目的 強制労働等により広島で被爆した同胞の慰霊と、再び原爆の惨事を繰り返さないことを願うため。 (碑文の一部の訳)
「悠久な歴史を通じて、わが韓民族は他民族のものをむさぼろうとしなかったし、他民族を侵略しようとはしませんでした。(中略)
しかし、5千年の長い民族の歴史を通じて、ここにまつった2万余位の霊が受けたような、悲しくも痛ましいことはかつてありませんでした。
韓民族が国のない悲しみを骨の髄まで味わったものが、この太平洋戦争を通してであり、その中でも頂点をなしたのが原爆投下の悲劇でありました。(以下略)」碑文 国文学者 韓 甲沫
明治維新以後、朝鮮支配を強めた日本は1910(明治43)年に朝鮮を完全な植民地にしました。土地を奪われた人々は大変苦しいめにあわされ、太平洋戦争が激しくなると人手不足を補うため強制連行や徴用によって日本に連れてこられ働かされました。
被爆当時、広島市に住んでいた数万人のうち、2万人余りが犠牲になったといわれます。
みかげ石の巨大な亀が、韓国の銘石で作られた碑柱を背負った高さ約5メートルの碑で、双龍の絵柄を刻んだ冠が被さっています。この碑は「なぜたくさんの朝鮮人が広島で被爆したのか」と問いつづけています。
碑石は韓国から運ばれたものです。本川橋西詰めにあったこの碑は、1999(平成11)年7月に現在の位置に移設されました。死没者名簿(2024 (令和6)年8月5日現在 2,814人)は、台座部分前方地面の箱の中に納められています。
表題揮毫 李孝祥
- 平和の灯(へいわのともしび)
-
平和の灯(へいわのともしび)
建立年月日 1964(昭和39)年8月1日 建立者 平和の灯建設委員会 設計者 丹下健三(当時・東大教授) 建立の目的 水を求めてやまなかった犠牲者を慰め、核兵器廃絶と世界恒久平和を希求するため。 全国12宗派35社寺・教会から寄せられた“宗教の火”、溶鉱炉などの全国の工場地帯から届けられた“産業の火”が、1945(昭和20)年8月6日生まれの7人の広島の乙女により点火されました。この火は、点火されて以来ずっと燃え続けており、核兵器廃絶まで燃え続ける灯を、日本全国民の平和の象徴にしたいとの願いが込められています。
- 平和乃観音像
-
平和乃観音像
建立年月日 1956(昭和31)年8月6日 建立者 中島本町会民 制作者 荒井秀山(あらいしゅうざん):彫刻家 建立の目的 無くなった町に対する惜別の情と犠牲者への慰霊のため 中島本町と、 この像が建っている平和記念公園の北側一帯は、幕末から明治・大正・昭和初期にかけて、市内有数の繁華街でした。
しかし原爆投下により、住民は438人(被爆後60日以内)が犠牲になりました。戦後、この地は生き残った人々がバラック小屋を作って、焼け跡に住みはじめたころ、 1949(昭和24)年に作られた広島平和記念都市建設法により、 公園建設となったため、転地を余儀なくされ、町は姿を消しました。再び根こそぎ消されていく古里への熱い思いと、亡くなった人たちへの慰霊の思いが、観音像の建立と町の復元地図の作成となりました。
- 広島平和都市記念碑(原爆死没者慰霊碑)
-
広島平和都市記念碑(原爆死没者慰霊碑)
建立年月日 1952(昭和27)年8月6日 設計 丹下健三(当時・東大助教授) 建立の目的 世界最初の原子爆弾によって壊滅した広島市を、平和都市として再建することを念願して設立したもの。 安らかに眠って下さい 過ちは 繰返しませぬから
雑賀忠義(さいがただよし)当時・広島大学教授形は、はにわの家型に造られており、犠牲者の霊を雨露から守りたいという気持ちを表しています。
中央の石室には、 国内外を問わず、 原子爆弾に被爆して亡くなられた方の氏名、年月日、年齢を記帳した原爆死没者名簿が納められています。 名前は毎年書き加えられています。 2024(令和6)年8月6日現在で129冊 (344,306名の名前が記帳された127冊、「氏名不詳者 多数」と記された中が白紙の1冊、 長崎で被爆死し遺族が広島に納めて欲しいと希望した13名の名前が書かれた長崎原爆死没者名簿 1冊)になっています。
毎年5月に名簿の「風通し」が行われています。 - 峠 三吉 詩碑
-
峠 三吉 詩碑
建立年月日 1963(昭和38)年8月6日 建立者 平和のための広島県文化会議 峠三吉詩碑建設委員会 建立の目的 占領軍の弾圧に屈せず、最後まで活動を続けた峠三吉の勇気と平和への熱意を讃えるとともに、 彼の遺志を継ぎ、核兵器廃絶の決意を新たにする。 峠三吉は28歳の時に、爆心地から約3キロメートル離れた翠町の自宅で被爆しました。戦後、青年運動・文化運動を通じ、次第に平和運動の先頭に立つようになり、原爆反対、平和擁護の作品を数多く発表しました。
1950(昭和25)年、朝鮮戦争が始まり、占領軍による原爆反対運動への弾圧が激しさを増す中、トルーマン大統領の "朝鮮戦争に原爆使用もありうる”という声明に触発され、「原爆詩集」をまとめる決意をしました。
この作品は、 1951(昭和26)年ベルリンの全世界青年学生平和祭に、日本の代表作品の一つとして送られ、 世界的な反響を与えました。 碑文はこの詩集の序として書かれたものです。
1953(昭和28)年3月10日死去、享年36歳でした。 - 原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑
-
原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑
建立年月日 1971(昭和46)年8月4日 建立者 原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑建設委員会 制作者 芥川永(あくたがわひさし)(当時・比治山女子短大教授) 建立の目的 原爆によって生命を奪われた子どもと教師を慰めるとともに、「三たび原爆を許してはいけない」という平和教育を、現在及び未来に推し進める決意を表す。 銘文
太き骨は 先生ならむ
そのそばに ちいさきあたまの骨
あつまれり正田 篠枝
米軍占領下の中で1946(昭和21)年広島刑務所の印刷部で秘密出版された歌集「さんげ」は、その後補完の上、被爆歌人の手記「耳鳴り」に「さんげ」として収録された。1938(昭和13)年国家総動員法により、学校も戦争体制になりました。
1941(昭和16)の国民学校令により小学校の呼び名も国民学校と変わり、現在の小学校にあたる初等科(6年制)と、中学校にあたる高等科(2年制)がありました。
戦争が激しくなると、都市部の初等科の3年生以上の児童は防空対策の一環として強制的に疎開させられました。 幼いため親元に残された1・2年生と、 建物疎開作業に従事させられた高等科の生徒が原爆の犠牲になりました。(この頃の夏休みは、8月10日から20日まででした。)正確にはわかりませんが、犠牲となったのは、教師約200人、子ども約2,000人と推定されています。
この場所では、毎年8月4日に、遺族、広島市内の小・中学校の児童・生徒の代表、教育関係者が多数参加して、慰霊祭を行っています。 - マルセル・ジュノー博士記念碑
-
マルセル・ジュノー博士記念碑
建立年月日 1979(昭和54)年9月8日 建立者 ジュノー博士記念碑建立会 製作者 芥川永(あくたがわひさし)(当時・比治山女子短大教授) 建立の目的 被爆者救護に人道的立場から尽力した博士の功績をたたえるため。 碑文
「1945年8月9日、赤十字国際委員会の駐日主席代表として来日 広島の原爆被災の惨状を聞くや直ちに占領軍総司令部へ行きヒロシマ救援を強く要請。9月8日調達した大量15屯の医薬品と共に廃墟の市街へ入り惨禍の実情を踏査 自らも被爆市民の治療にあたる。
博士の尽力でもたらされた医薬品は市内各救護所へ配布 数知れぬ被爆者を救う 博士の人道的行為に感謝し 国際赤十字のヒューマニズムを讃え永く記念してこれを建てる」裏面の碑文
「無数の叫びがあなたたちの助けを求めている
M.ジュノー著「第三の兵士」より」マルセル・ジュノー博士(1904年~1961年)
スイスの医学者。彼の来日した当初の目的は、連合軍捕虜などの動静を調査することでした。
しかし、原爆被害の惨状を知ると直ちに連合国最高司令官総司令部へ救援を要請し、調達した医薬品を持って9月8日に広島入りしました。現地では、被害調査に当たるとともに自らも治療に携わりました。 - 広島市立高等女学校原爆慰霊碑
-
広島市立高等女学校原爆慰霊碑
建立年月日 1948(昭和23)年8月6日 建立者 広島市女原爆遺族会 設計者 河内山賢祐(こうちやまけんすけ):彫刻家 建立の目的 原爆の犠牲となった職員生徒の慰霊 碑文(裏面)
「友垣にまもられながらやすらかに ねむれみたまよ このくさ山に」
(宮川雅臣:当時の校長)現在の平和記念資料館~平和大通り一帯(爆心地から約500m。当時は材木町~木挽町)の建物疎開作業に来ていた1、2年生541人、職員10人は、全員が亡くなりました。同校では他の動員先を含め676人が被爆死し、市内の学校では最も多くの犠牲者を出しています。
中央で、E=MC²と刻んだ箱を抱え、天使の翼をもつ制服・モンペ姿の少女は犠牲となったことを表し、両側から友のささげる花輪(慰霊)とハト(平和)に守られています。
E=MC²
原爆の原理になったアインシュタインの相対性理論からとられた原子力エネルギーの公式です。連合軍の占領下、「原爆」という文字が使用できなかった当時の事情を表しています。碑の移設
1946(昭和21)年、現在の平和大通りの場所に木碑の供養塔が建てられ、3回忌まではそこで慰霊祭が行われていました。現在の碑は、1948(昭和23)年に学校の奉安殿跡の草山に建てられたものです。当時は占領下で慰霊碑の建立が許されず、「平和塔」の名で建立されました。被災地近くの現在地に移設されたのは、13回忌の1957(昭和32)年6月20日です。 - 嵐の中の母子像
-
嵐の中の母子像
建立年月日 1960(昭和35)年8月5日 制作者 本郷新(ほんごうしん):彫刻家 建立者 広島市婦人会連合会 建立の目的 核兵器廃絶への限りない努力を呼びかける。
私達は、広島の母としての決意を示すとともに、ここを訪れる全ての人々に無言の訴えを続けるため、この像を建てたい。」とあります。1959(昭和34)年、第5回原水爆禁止世界大会が広島で開かれた折、原水爆禁止日本協議会から当時の浜井広島市長に、原水爆禁止運動推進への感謝のしるしとして、この像の原型となった石こう像が贈られました。
その後、この大会の成功のため尽力した広島市婦人会連合会が「平和記念公園への設置」 を呼びかけ、ブロンズ像にするための募金活動を行い建立され、広島市に寄贈されたものです。像の原型となった石こう像は、現在、札幌市にある本郷新記念館(札幌彫刻美術館)に展示されています。
襲いかかる業苦に耐え、悲しみを乗り越えていく母親の強い愛情を示す像に市民の平和への願いを託しています。
- 広島平和記念資料館
-
広島平和記念資料館

開館年月日 1955(昭和30)年8月24日 直近の改修 2017(平成29)年4月東館改修 2019(平成31)4月本館改修 建立者 広島市 設計者 丹下健三、浅田孝、大谷幸夫、木村徳国 (きむらのりくに) 形状 東館: 地上3階地下1階建 延床面積 10,098m²
本館: 地上2階一部中3階建 延床面積 1,615m²
ピロティー式(建築の地上部分を柱のみで支持し開放されている)の本館下の空間は、廃墟の中から立ち上がる人間の力強さを表したいという考えが込められている。建立の目的 原子爆弾による被害の実相を世界中の人々に伝え、ヒロシマの心である核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に寄与すること。 1949(昭和24)年9月、広島市中央公民館に「原爆参考資料陳列室」が設置され、原爆被災資料の展示が始まりました。 また、 同年公布された 「広島平和記都市建設法」に基づき、平和記念公園の中に、 1955(昭和30)年6月に平和記念館が、8月に平和記念資料館(現: 本館)が開館しました。
1994(平成6)年6月、展示・収蔵機能や平和学習の場を充実するため、 平和記念館を建て替え、 2館を一体化した新たな「平和記念資料館」(現:東館)として開館し、現在に至っています。
2006(平成18)年7月5日には、 平和記念資料館の本館部分が国の重要文化財に指定されました。戦後建築としては初めての重要文化財です。
2025年度 組合員を対象とした定例碑めぐりのご案内
組合員を対象にした自由参加の碑めぐりです。平和公園内・外をご案内します。
| 月日 | 時間 | コース | 集合場所 | ご案内予定の碑や史跡 |
|---|---|---|---|---|
| 4月5日(土) | 10:00~12:00 | 国泰寺・大手町地域 | 白神社前 | 第一県女の碑、一中、広島市役所資料展示室 他 |
| 5月3日(土) | 10:00~12:00 | 広島城 | 表御門 | 中国軍管区司令部跡、大本営跡、陸軍幼年学校跡 他 |
| 6月7日(土) | 10:00~12:00 | 平和記念公園 | 平和記念資料館入口辺り | 平和記念公園内の主要な碑をご案内します |
| 7月5日(土) | 10:00~12:00 | 袋町地域 | 袋町小学校平和資料館前 | 袋町小平和資料館、旧日本銀行広島支店、白神社 他 |
| 9月6日(土) | 10:00~12:00 | 本川地域 | 相生橋西詰南側 | 本川小平和資料館、清住寺、空鞘神社 他 |
| 10月4日(土) | 10:00~12:00 | 平和記念公園 |
原爆ドーム北側 (電車通り側) |
平和記念公園内の主要な碑をご案内します |
| 11月1日(土) | 10:00~12:00 | 千田地域 | 御幸橋西詰北側 | 御幸橋、広電変電所、赤十字病院Mパーク、広大跡地 他 |
| 12月6日(土) | 10:00~12:00 | 比治山 | 比治山下電停前 | 多聞院、旧ABCC(放射線影響研究所)、陸軍墓地 他 |
| 1月10日(土) | 10:00~12:00 | 平和記念公園 | 平和記念資料館入口辺り | 平和記念公園内の主要な碑をご案内いたします |
| 2月7日(土) | 10:00~12:00 | 平和記念公園 |
原爆ドーム北側 (電車通り側) |
平和記念公園内の主要な碑をご案内いたします |
| 3月7日(土) | 10:00~12:00 | 平和記念公園 | 平和記念資料館入口辺り | 平和記念公園内の主要な碑をご案内いたします |
- 集合場所に碑めぐりガイドが立っています。いずれのコースも10時に出発します。
- 参加費無料。ガイドブックが必要な方は平和公園内150円、公園外50円で当日、購入できます。
碑めぐりガイドについて
平和記念公園をご案内します
「広島市内5コース」のご紹介
原爆の傷跡を残すモニュメントは、平和記念公園の中だけではありません。広島市内全域の碑めぐりガイドブックもございます。もちろん、碑めぐりガイドによるご案内も可能です。お気軽にお問い合せください。
コース名
- 本川地域
- 袋町地域
- 広島城地域
- 千田地域
- 比治山地域
修学旅行などで碑めぐりをご希望の方へ(旅行会社の方もご参照ください)
下記「よくいただくお問合せ」をご確認の上お申し込みください。上記「広島市内5コース」のご案内については、コースによっては所要時間も変わりますので、ご相談ください。
| ガイド料 | 碑めぐりガイド1名につき¥5000 |
|---|---|
| ガイド時間 | おおむね1時間~2時間程度 |
碑めぐりガイド(団体)お申込みはこちら
お問い合わせはこちら
生協ひろしま大野事務所 組織運営部 くらし応援グループ
担当 大原まで
こちらはお問い合わせ専用です。
碑めぐりガイドのお申込みはWEB申込みからお願いいたします。
よくいただくお問い合わせ
- ○月○日にガイドをお願いしたいのですが?
- WEB申込みから碑めぐりガイド申込フォームに必要事項を記入し、お申し込みください。碑めぐりガイドの会メンバーの活動日程を確認後、受けられるかどうかの連絡をいたします。
用紙の記入方法など分からない場合はお問合わせください。春・秋の修学旅行期には、前後で他団体の申込を受けていることがありますので、いったんお受けした日時での変更は難しいことがあります。変更・キャンセルはできるだけ早めに連絡をいただきますようお願いいたします。
- 100名の生徒が行きますが、何人くらいガイドをお願いすればいい?
- 歩きながら、「碑」の前で説明をしますので、理想は1グループ10名くらい。 100名だったら10名程度のガイドで説明をさせていただくのがよいかと思います。その他、ご希望がございましたら相談ください。
- ガイドは被爆者の方ですか?
- 生協ひろしまの碑めぐりガイドは被爆者ではありません。被爆者の方はご高齢の方が多く、歩きながらの説明が難しい方が多くなってきています。被爆の体験はしていないけれど「語り継いで」いくことを大切に考え、学習や研修を重ねて被爆の実相を伝えています。(最近は、被爆体験を被爆者の方に聞いたあと、碑めぐりを私どもで行うというパターンも増えてきています。)
- 時間はどれくらいかかりますか
- 上記地図上にある碑をご案内いたします。約1.5時間から2時間です。折り鶴を奉納したい等の希望があれば、申込用紙にその旨ご記入ください。
- 集合場所はどこを指定したらよいですか?
- 広島平和資料館の入り口、原爆ドーム前というパターンが多いのですが、平和記念公園までの交通手段によって、出発点を検討されることをおすすめします。地図に集合場所のポイントを示しておりますので、参考にしてください。
集合場所の地図
- 5000円以外にお金はかかりますか?
- 交通費も込みの金額ですので、一切かかりません
- お金はどのようにして払えばいい?
- 当日、ガイドの担当者にまとめて現金でお支払いください。(例)ガイド5名分(25,000円)を封筒に入れてください。領収書はお申込み時に入力された領収書宛名で発行します。
- 領収書はインボイス対応ですか?
- 生協組合員の有志で活動する特定団体のため、インボイス対応の領収書ではございません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
- ガイドさんと直接打ち合わせがしたい
- 碑めぐりガイドはボランティアグループです。連絡先は「自宅」ということになってしまいますので、直接の連絡はご遠慮願います。必要に応じて、碑めぐりの代表の方の連絡先をご案内させていただきます。
- ガイドさんに、子どもたちからお礼の手紙が書きたいのですが
- ありがとうございます。ガイドさんたちも、子どもさんたちから、手紙をいただいた時、「ガイドをやっていてよかった」と思うそうです。上記の住所にお送りください。碑めぐりガイドの会が定期的に開催する会議で手渡します。